
もくじ
午前 問1
元素記号Fの同族元素はどれか。
- C
- O
- P
- Cl
- Ar
解説
フッ素(F)は17族元素で塩素(Cl)、臭素(Br)、ヨウ素(I)、アスタチン(At)が属する。
答え 4
午前 問2
核反応について正しいのはどれか。
- Q値が正の場合は吸熱反応である。
- 荷電粒子の加速に原子炉が使われる。
- 中性子の加速にサイクロトロンが使われる。
- 入射粒子が中性子のときクーロン障壁の影響を受ける。
- 反応を起こすために必要な最小エネルギーをしきい値と呼ぶ。
解説
- Q値が正の場合は発熱反応
- 原子炉は中性子を発生させる装置である
- 中性子は電荷を持たないのでサイクロトロンで加速できない
- 中性子は電荷を持たないのでクーロン障壁の影響を受けない
答え 5
午前 問3
放射性核種の分離法について正しいのはどれか。
- 電気泳動法では加熱を行う。
- ペーパークロマトグラフィではRf値を比較する。
- 薄層クロマトグラフィでは移動相でキャリアガスを用いる。
- 共沈法では不要な放射性核種を沈殿させるために捕集剤を用いる。
- イオン交換クロマトグラフィでは分離のスピードを上げるためにポンプを用いる。
解説
- 電気泳動法はイオン化傾向の違いを利用する
- 薄層クロマトグラフィでは移動相は溶媒
- ガスクロマトグラフィでは移動相でキャリアガスを用いる
- 共沈法では不要な放射性核種を沈殿させるためにスカベンジャーを用いる
- 捕集剤は目的核種を集めるために用いる
- 高速液体クロマトグラフィでは分離のスピードを上げるためにポンプを用いる
答え 2
午前 問4
標識化合物の分解について正しいのはどれか。
- 分解速度はγ線で最も大きい。
- 細菌やカビによる分解を考慮する必要はない。
- 放射性壊変による分解を防止する方法はない。
- 放射線分解の起こりやすさは比放射能に関係しない。
- ラジカルによる分解を防止するには有酸素状態が望ましい。
解説
- 分解速度は飛程の短いα線やβ線で大きくなる
- 細菌やカビによる分解を考慮して無菌・低温保存が望ましい
- 比放射能が高いほど放射線分解は起こりやすくなる
- ラジカルによる分解を防止するには無酸素状態が望ましい
答え 3
午前 問5
X線照射野と光照射野のずれを図に示す。
ずれがJIS規格の許容値を超えないのはどれか。
ただし、X線は実線、光は破線、焦点から光照射野までの距離は110cm、図中の単位はcmとする。
- A
- B
- C
- D
- E
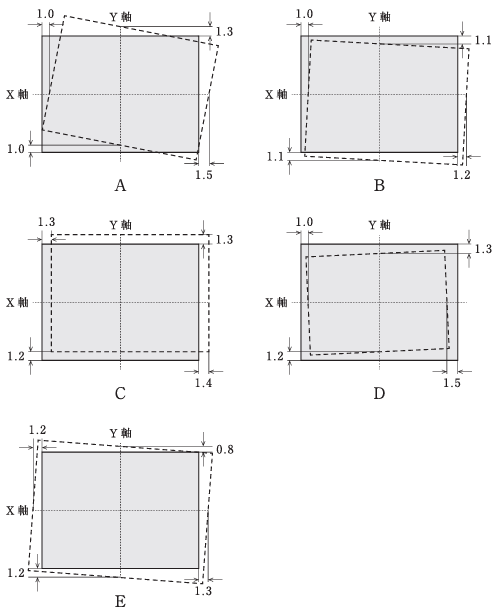
解説
焦点から光照射野までの距離の±2%以内、垂直度の誤差は3°以内としなければならない
詳しくは診断用X線可動絞りガイドを参照
選択肢ではBの1.0+1.2=2.2と、1.1+1.1=2.2で±2%以内に収まっている
答え 2